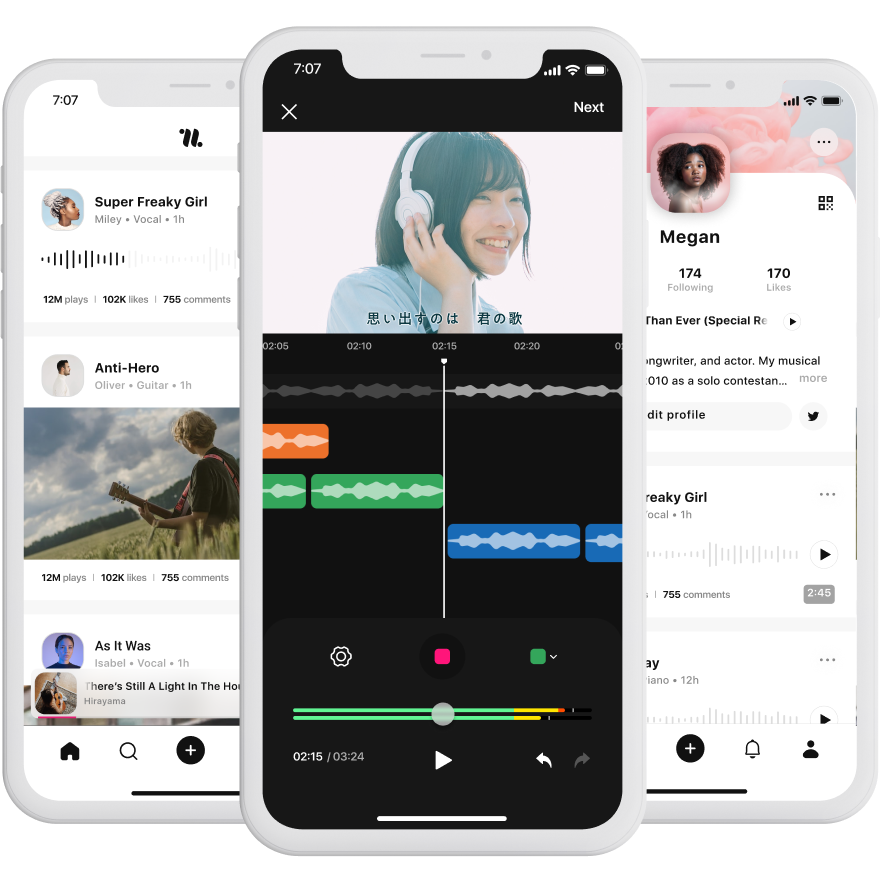【長編声劇】記憶の片隅に、並行小説、番宣
カテゴリ
企画・募集
メンバー8
コメント1
【7月15日番宣開始】
【8月第一日曜日本編開始】
する長編声劇記憶の片隅に!
こちらはそんな記憶の片隅にの、より詳しい情景描写などが掲載されていく、小説投稿コミュニティです。
不定期にはなるかもしれませんが、基本本編と併せて並行に進めさせていただきます!!
こちらを読んでみて、自分もキャストとして参加したいと思った方はこちらのURLよりご応募ください!
https://nana-music.com/communities/519790/
また、誤字脱字や、小説への感想、声劇やキャストへの感想もこちらのコミュニティよりお待ちしております!!
https://nana-music.com/communities/578584/
皆様に愛される物語を作れるよう、主催兼物語制作担当として努めさせていただきますので、よろしくお願いします!!
 行無舟人その都度、空を飛ぶ記憶が自分の中に、体験した事のように流れていく。だからと言って、それがずっと記憶として保有されるわけでもなく、それを食事として食べ、消化していく。だから、彼らの生きた証は、消えてしまう。 その罪悪感に耐えかねて自殺する霊弔も、たまに耳にする。 だがそれは、悲しいニュースとしてではなく、様々な意見があるなかで、大抵は、仕方のないことだと締め括られる。食べてはならないのだから、それ以外の選択肢はないだろう。と、述べる学者もいた。そんな中で、記憶を食べるのは好まなかった。自分が人ではないみたいで───それでも、ゾンビが血肉に飢えるように、僕らもまた、記憶をあまりにも食べないと、見境なく記憶を食らいついてしまう。だからこそ、定期的に記憶を少しでも、いただいていた。 「ご馳走様でした」 指に止まる鳥に言った。なにをされたか分からないと言うように首を傾げる鳥に、僕は微笑んだ。どことなく現実から目を反らせられるような気分になるから。その一瞬の後で、上空に鳥を羽ばたかせる。 鳥が翼を広げて飛んでいく光景を見ては、記憶を取りすぎていないと安堵すると同時に、奥底で、罪悪感が蓄積されていく。 その僅かな時間を噛み殺すように、辺りを見回すと、騒々しく楽器の音やボールの弾む音、そしてクラクションや人が話す音がひっきりなしに聞こえ始める。 放課後の時間が、僕ら霊弔にとって、一番恐怖な時間だった。唯一、疑われない業務や授業と言うものから解放されてしまうからだ。慌てるように踵を返し、屋上を後にする。階段を駆け下りて、バッグを取りに行くと、教室で秋が携帯を見ていた。席は僕の席。恐らくまた、部活に行こうと言うのだろう。彼なりの優しさに、先ほどの非人道的行為を思い出し、罪悪感がまたも膨れ上がっていく。それを勘づかれないよう、取り繕って秋に話しかける。 「お疲れ秋」 後ろから声を掛けると、秋が言う。 「今日部活は?」と。 何度も僕を部活に戻そうと声を掛けてくれる。その度に否定の返事をしては、申し訳なさそうに帰宅する。秋と一緒にいたくないとか、一人でいたい訳ではない。何も考えずに、自分のペースでいられることが、自分の心を落ち着かせる。人の目がない自分の部屋だけが、心の安らぐ場所だから。けれどその生活は、心にぽっかりと穴を開けていく。 「ごめん、今日も・・・」 「そっか」 聞きなれてしまったであろう言葉にも、少し悲しそうに微笑む秋。現実から目を反らそうと振り返ると、秋が言った。 「一馬、俺ずっとお前の親友だから」 心に響く言葉。しかし、真実も話せていない僕が、秋に掛ける言葉なんて、見当たらなかった。 「ありがとな」 たったの五文字。その言葉に、申し訳ない気持ちを乗せて、廊下へと出る。その時、前方を歩く二人のクラスメートが僕に手を振った。 「一馬君、ばいばい」 「あぁ、じゃあ」 普段は声を駆けてこない二人。社交辞令かのようにそう言って歩き出そうとしたとき、教室から声が響いた。 「秋くん」 「なに?」 三人だけの教室、僕は何かが引っ掛かり、そっと教室へと歩み寄った。 「一馬君ってさ、霊弔なの? そんな噂が広まってて、信じてる訳ではないんだけど」 「なに言って・・・」 「屋上で記憶を食べてたって」 「そんなの嘘だろ。記憶食べてるかどうかなんて俺らには分からないし、適当にみんなが言ってるんだろ」 「そう、だよね・・・」 「当たり前だろ」 秋の言葉を聞いて、泣き出しそうな気持ちを抑えながら、走り去っていた。 見られてた。いつか分からないけれど確実に。例え食らうところを始めてみたのだとしても、霊弔だって分かるはずだ。食らうその瞬間、僕らは記憶を保ってはいないが、狂喜的な顔になると、霊弔学で先生が言っていたのだから。 「人のことを襲う・・・一馬、本当に大丈夫なんだよな?」 秋の、不安と心配の声は、僕に届くこともなく、一人になった教室のなかで、ポツリと囁かれた。
行無舟人その都度、空を飛ぶ記憶が自分の中に、体験した事のように流れていく。だからと言って、それがずっと記憶として保有されるわけでもなく、それを食事として食べ、消化していく。だから、彼らの生きた証は、消えてしまう。 その罪悪感に耐えかねて自殺する霊弔も、たまに耳にする。 だがそれは、悲しいニュースとしてではなく、様々な意見があるなかで、大抵は、仕方のないことだと締め括られる。食べてはならないのだから、それ以外の選択肢はないだろう。と、述べる学者もいた。そんな中で、記憶を食べるのは好まなかった。自分が人ではないみたいで───それでも、ゾンビが血肉に飢えるように、僕らもまた、記憶をあまりにも食べないと、見境なく記憶を食らいついてしまう。だからこそ、定期的に記憶を少しでも、いただいていた。 「ご馳走様でした」 指に止まる鳥に言った。なにをされたか分からないと言うように首を傾げる鳥に、僕は微笑んだ。どことなく現実から目を反らせられるような気分になるから。その一瞬の後で、上空に鳥を羽ばたかせる。 鳥が翼を広げて飛んでいく光景を見ては、記憶を取りすぎていないと安堵すると同時に、奥底で、罪悪感が蓄積されていく。 その僅かな時間を噛み殺すように、辺りを見回すと、騒々しく楽器の音やボールの弾む音、そしてクラクションや人が話す音がひっきりなしに聞こえ始める。 放課後の時間が、僕ら霊弔にとって、一番恐怖な時間だった。唯一、疑われない業務や授業と言うものから解放されてしまうからだ。慌てるように踵を返し、屋上を後にする。階段を駆け下りて、バッグを取りに行くと、教室で秋が携帯を見ていた。席は僕の席。恐らくまた、部活に行こうと言うのだろう。彼なりの優しさに、先ほどの非人道的行為を思い出し、罪悪感がまたも膨れ上がっていく。それを勘づかれないよう、取り繕って秋に話しかける。 「お疲れ秋」 後ろから声を掛けると、秋が言う。 「今日部活は?」と。 何度も僕を部活に戻そうと声を掛けてくれる。その度に否定の返事をしては、申し訳なさそうに帰宅する。秋と一緒にいたくないとか、一人でいたい訳ではない。何も考えずに、自分のペースでいられることが、自分の心を落ち着かせる。人の目がない自分の部屋だけが、心の安らぐ場所だから。けれどその生活は、心にぽっかりと穴を開けていく。 「ごめん、今日も・・・」 「そっか」 聞きなれてしまったであろう言葉にも、少し悲しそうに微笑む秋。現実から目を反らそうと振り返ると、秋が言った。 「一馬、俺ずっとお前の親友だから」 心に響く言葉。しかし、真実も話せていない僕が、秋に掛ける言葉なんて、見当たらなかった。 「ありがとな」 たったの五文字。その言葉に、申し訳ない気持ちを乗せて、廊下へと出る。その時、前方を歩く二人のクラスメートが僕に手を振った。 「一馬君、ばいばい」 「あぁ、じゃあ」 普段は声を駆けてこない二人。社交辞令かのようにそう言って歩き出そうとしたとき、教室から声が響いた。 「秋くん」 「なに?」 三人だけの教室、僕は何かが引っ掛かり、そっと教室へと歩み寄った。 「一馬君ってさ、霊弔なの? そんな噂が広まってて、信じてる訳ではないんだけど」 「なに言って・・・」 「屋上で記憶を食べてたって」 「そんなの嘘だろ。記憶食べてるかどうかなんて俺らには分からないし、適当にみんなが言ってるんだろ」 「そう、だよね・・・」 「当たり前だろ」 秋の言葉を聞いて、泣き出しそうな気持ちを抑えながら、走り去っていた。 見られてた。いつか分からないけれど確実に。例え食らうところを始めてみたのだとしても、霊弔だって分かるはずだ。食らうその瞬間、僕らは記憶を保ってはいないが、狂喜的な顔になると、霊弔学で先生が言っていたのだから。 「人のことを襲う・・・一馬、本当に大丈夫なんだよな?」 秋の、不安と心配の声は、僕に届くこともなく、一人になった教室のなかで、ポツリと囁かれた。